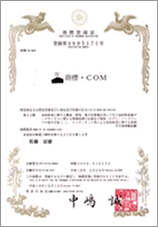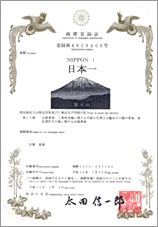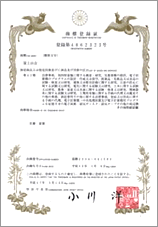吸音断熱材及びその製造方法
(書誌+要約+請求の範囲)
(19)【発行国】日本国特許庁(JP)
【公報種別】再公表特許(A1)
(11)【国際公開番号】WO98/38140
【発行日】平成11年(1999)7月6日
(54)【発明の名称】吸音断熱材及びその製造方法
(51)【国際特許分類第6版】
C04B 35/52
E04B 1/82
【審査請求】有
【予備審査請求】有
【全頁数】44
【出願番号】特願平10−537490
(21)【国際出願番号】PCT/JP97/00598
(22)【国際出願日】平成9年(1997)2月27日
(43)【国際公開日】平成10年(1998)9月3日
(81)【指定国】EP(AT,BE,CH,DE,DK,ES,FI,FR,GB,GR,IE,IT,LU,MC,NL,PT,SE),JP,US
(71)【出願人】
【氏名又は名称】大阪瓦斯株式会社
【住所又は居所】大阪府大阪市中央区平野町4丁目1番2号
(72)【発明者】
【氏名】町野 史和
【住所又は居所】大阪府大阪市中央区平野町4丁目1番2号 大阪瓦斯株式会社内
(72)【発明者】
【氏名】肥後 強
【住所又は居所】大阪府大阪市中央区平野町4丁目1番2号 大阪瓦斯株式会社内
(72)【発明者】
【氏名】片岡 利展
【住所又は居所】大阪府大阪市中央区平野町4丁目1番2号 大阪瓦斯株式会社内
(72)【発明者】
【氏名】尾上 良一
【住所又は居所】大阪府大阪市中央区平野町4丁目1番2号 大阪瓦斯株式会社内
(72)【発明者】
【氏名】伊達 利夫
【住所又は居所】大阪府大阪市中央区平野町4丁目1番2号 大阪瓦斯株式会社内
(72)【発明者】
【氏名】佐藤 富徳
【住所又は居所】大阪府大阪市中央区平野町4丁目1番2号 大阪瓦斯株式会社内
(74)【代理人】
【弁理士】
【氏名又は名称】大前 要
(57)【要約】
炭素繊維を構成素材として、耐久性、圧縮復元性、軽量性、火災に対する安全性に優れ、かつ非電気腐食性にも優れた吸音断熱材を提供する。この吸音断熱材は、平均直径0.5μm〜5μm、平均繊維長1mm〜15mmの炭素繊維からなる綿状炭素繊維集合体の繊維相互が熱硬化性樹脂で接合された吸音断熱材であり、かつ前記吸音断熱材を一方電極とし、アルミニウム板を他方電極とし、0.45重量%塩化ナトリウム水溶液を電解液とするガルバニックセルにおけるガルバニック電流が10μA以下であることを特徴とする。
【特許請求の範囲】
(1) 平均繊維直径0.5μm〜5μm、平均繊維長1mm〜15mmの炭素繊維からなる綿状炭素繊維集合体の繊維相互が熱硬化性樹脂で接合されている吸音断部材。
(2) 前記吸音断熱材を一方電極とし、アルミニウム板を他方電極とし、0.
45重量%塩化ナトリウム水溶液を電解液とするガルバニックセルにおけるガルバニック電流が10μA以下であることを特徴とする、請求項1記載の吸音断熱材。
(3) 前記吸音断熱材の嵩密度が3Kg/m3以上、10Kg/m3以下である、請求項1または2記載の吸音断熱材。
(4) 前記吸音断熱材の最大引張強度が1.0g/mm2以上である、請求項1ないし3記載の吸音断熱材。
(5) 前記吸音断熱材の圧縮復元率が70%以上である、請求項1ないし4記載の吸音断熱材。
(6) 前記吸音断熱材の最大引張強度方向に直交する方向における最小引張強度が前記最大引張強度の0.04倍以上であり、前記最大引張強度方向と前記最小引張強度の方向の双方に直交する方向の引張強度が前記最大引張強度の0.76倍以上である、請求項1ないし5記載の吸音断熱材。
(7) 前記吸音断熱材の熱伝導率が0.039W/m・℃以下である、請求項1ないし6記載の吸音断熱材。
(8) 前記吸音断熱材の25mm厚における周波数1000Hzでの垂直入射吸音率が48%以上である、請求項1ないし7記載の吸音断熱材。
(9) 前記炭素繊維が縮合多環炭化水素を重合して得た異方性ピッチからなるものである、請求項1ないし8記載の吸音断熱材。
(10) 縮合多環炭化水素を重合して得た異方性ピッチを加熱溶融し、この溶融物を紡糸ノズルから吐出するとともに、前記紡糸ノズルの周囲から前記溶融物の吐出方向と同方向に加熱ガスを噴出させることによって紡糸する紡糸工程と、 紡糸した繊維を不融化した後、650℃以上、750℃未満の温度で炭化処理して非電食性炭素繊維を作製する炭素繊維作製工程と、 前記非電食性炭素繊維を熱硬化性樹脂液を噴霧しながら平面上に綿状に堆積する噴霧堆積工程と、 噴霧堆積したものを加熱成形する加熱成形工程と、 を備える吸音断熱材の製造方法。
(11) 前記噴霧堆積工程が、前記非電食性炭素繊維を綿状に堆積する堆積工程と、この綿状の炭素繊維堆積物に熱硬化性樹脂液を噴霧する噴霧工程とからなることを特徴とする、請求項10記載の吸音断熱材の製造方法。
(12) 前記噴霧堆積工程または前記堆積工程における堆積方法が、空気で開繊した炭素繊維を少なくとも100cm以上の高さから平面上に落下させて行うことを特徴とする、請求項10または11記載の吸音断熱材の製造方法。
(13) 前記綿状の炭素繊維堆積物の嵩密度が1.3Kg/m3以下であることを特徴とする、請求項11または12記載の吸音断熱材の製造方法。
詳細な説明
【発明の詳細な説明】
吸音断熱材及びその製造方法 技術分野 この発明は、炭素繊維を用いた吸音断熱材に関し、詳しくは非電食性の極細の炭素繊維を用いた吸音断熱材に関する。
この発明にいう吸音断熱材は、吸音断熱を目的とするものに限られず、専ら吸音を目的とする吸音材として、または専ら断熱を目的とする断熱材としても使用できる。
背景技術 吸音断熱材は、省エネルギー型の快適な居住空間を作るための部材として、或いは厳しい外部環境から人や器機等を保護するための部材として益々重要性が高まっている。吸音断熱材には、従来、天然繊維や合成樹脂が使用されていたが、これらの繊維は一般に可燃性であり、火災のとき有毒ガスを発生する。よって、安全性に問題がある。
このため、これらの素材に代えて今日では無機質材料が用いられるようになってきており、特にガラス繊維は火災に対する安全性や成形性・施工性が良いため、吸音断熱材の素材として広く使用されるようになっている。
しかし、ガラス繊維は比重が2.4〜2.6g/cm3程度と大きい。このため、ガラス繊維を用いた吸音断熱材は、単位重量当たりの吸音断熱性が十分ではないという問題がある。また、ガラス繊維は吸湿することにより徐々に劣化すると共に、機械的強度も弱い。よって、ガラス繊維を用いた吸音断熱材は、耐久性が十分でないという問題がある。
その一方、今日では安全で高性能な吸音断熱材に対する必要性が益々増大している。例えば高速鉄道車両、航空機、宇宙船等の高速輸送手段においては、高速性、快適性等を追求する必然として、高度な安全性、耐久性、軽量性等を備えた吸音断熱材が要求されている。具体的には、優れた吸音断熱性能に加え、■軽量であること、■耐炎性に優れること、■火災のとき有毒ガスを発生しないこと、■構造部材に対する腐食性がないこと、■機械的強度や圧縮復元性に優れること、■耐磨耗性に優れること、■吸湿性がすくないこと、■施工性がよいことなどが要求されている。
然るに、上記のごとく、ガラス繊維製の吸音断熱材を含め従来の吸音断熱材は、これらの用途において十分な信頼性をもって使用できるものではない。このため、上記の用途において高い信頼性をもって使用できる吸音断熱材の開発が待たれている。
発明の開示 本発明は、上述に鑑み、炭素繊維を用いて吸音性や断熱性に優れることはもとより、耐久性、機械的強度や圧縮復元性、軽量性、化学的安定性、難燃性、火災時において有毒ガスを発生しない性質、吸湿しにくい性質に優れ、かつ非電気腐食性や非導電特性にも優れた吸音断熱材を提供しようとするものである。
ところで、炭素繊維は一般に電気導電性が高く制電特性に優れ、また比較的起電力が大きい。よって、このような炭素繊維の特性は、従来より帯電防止等に活用されている。しかしながら、炭素繊維のこの特性は、吸音断熱材の素材としては好ましくない。
なぜなら、電気導電性の高い素材を用いて吸音断熱材を構成した場合、吸音断熱材自体が電気短絡の原因となると共に、吸音断熱材から脱落し浮遊する素材片が電気回路等の内部に入りこみ内部短絡の原因となる。また、起電力を有する素材であると、その周囲の他の部材との間で電気化学反応を生じ、結果として他の部材を電気腐食する恐れがあるからである。
しかして、本発明は高速鉄道車両や航空機等に実装可能な吸音断熱材を提供することを目的とする。ところが、高速鉄道車両等は一般に金属を主構成材料としており、また電気配線の多い構造物である。よって、単にガラス繊維に代えて炭素繊維を用いて吸音断熱材を組成しても、本発明の課題が解決できない。
そこで、本発明者らは、炭素繊維を用いて上記課題を達成し得る手段について鋭意研究した。その結果、炭素繊維の炭化処理温度を適正に設定することにより、吸音断熱材の強度や吸音断熱性能を向上させ、同時に電気腐食性をも改善できることを見出した。また、炭素繊維を素材とする吸音断熱材による電気腐食は、吸音断熱材のガルバニック電流を10μA以下とすることにより実質的に防止できることを見出した。この知見に基づいて、下記構成の一群の本発明を完成した。
なお、電気導電性の良否と電気腐食性とは、必ずしも一義的な関係にない。よって本発明で規定するガルバニック電流値は、電気腐食を起こさない吸音断熱材となす要件として極めて重要な意義を有する。
一群の本発明は次の構成を有する。
(1)第1の発明は、平均繊維直径0.5μm〜5μm、平均繊維長1mm〜15mmの炭素繊維からなる綿状炭素繊維集合体の繊維相互が熱硬化性樹脂で接合されていることを特徴とする吸音断熱材である。
(2)第2の発明は、上記第1の発明において、前記吸音断熱材を一方電極とし、アルミニウム板を他方電極とし、0.45重量%塩化ナトリウム水溶液を電解液とするガルバニックセルにおけるガルバニック電流が10μA以下であることを特徴とする。
(3)第3の発明は、上記第1または第2の発明において、前記吸音断熱材の嵩密度が3Kg/m3以上、10Kg/m3以下であることを特徴とする。
(4)第4の発明は、上記第1ないし第3の発明において、前記吸音断熱材の最大引張強度が1.0g/mm2以上であることを特徴とする。
(5)第5の発明は、上記第1ないし第4の発明において、前記吸音断熱材の圧縮復元率が70%以上であることを特徴とする。
(6)第6の発明は、上記第1ないし第5の発明において、前記吸音断熱材の最大引張強度方向に直交する方向における最小引張強度が前記最大引張強度の0.04倍以上であり、かつ前記最大引張強度方向と前記最小引張強度の方向の双方に直交する方向の引張強度が前記最大引張強度の0.76倍以上であることを特徴とする。
(7)第7の発明は、上記第1ないし第6の発明において、前記吸音断熱材の熱伝導率が0.039W/m・℃以下であることを特徴とする。
(8)第8の発明は、上記第1ないし第7の発明において、前記吸音断熱材の25mm厚における周波数1000Hzでの垂直入射吸音率が48%以上であることを特徴とする。
(9)第9の発明は、上記第1ないし第8の発明において、前記炭素繊維が縮合多環炭化水素を重合して得た異方性ピッチからなるものであることを特徴とする。
(10)第10の発明は、縮合多環炭化水素を重合して得た異方性ピッチを加熱溶融し、この溶融物を紡糸ノズルから吐出するとともに、前記紡糸ノズルの周囲から前記溶融物の吐出方向と同方向に加熱ガスを噴出させることによって紡糸する紡糸工程と、紡糸した繊維を不融化した後、650℃以上、750℃未満の温度で炭化処理して非電食性炭素繊維を作製する炭素繊維作製工程と、前記非電食性炭素繊維を熱硬化性樹脂液を噴霧しながら平面上に綿状に堆積する噴霧堆積工程と、噴霧堆積したものを加熱成形する加熱成形工程と、を備える吸音断熱材の製造方法である。
(11)第11の発明は、上記第10の発明において、前記噴霧堆積工程が、前記非電食性炭素繊維を綿状に堆積する堆積工程と、この綿状の炭素繊維堆積物に熱硬化性樹脂液を噴霧する噴霧工程とからなることを特徴とする。
(12)第12の発明は、上記第10または第11の発明において、前記噴霧堆積工程または前記堆積工程における堆積方法が、空気で開繊した炭素繊維を少なくとも100cm以上の高さから平面上に落下させて行うことを特徴とする。
(13)第13の発明は、上記第11または第12の発明において、前記綿状の炭素繊維堆積物の嵩密度が1.3Kg/m3以下であることを特徴とする。
ここで、上記における引張強度は、定速緊張型引張試験機を用い、引張速度20mm/min、試料長50mm、試料サイズ50mm×50mm×25mm厚(図15、図16参照)で測定した値である。引張試験方法の詳細は、後記の〔引張強度の測定条件〕の通りである。
熱伝導率は、ASTM C−518(American Society for Testing and Material ;熱流計法)に従い温度22°Cで測定した値である。
垂直入射吸音率は、JIS A−1405に従い測定した値である。
圧縮復元率は、100mm×100mm×厚み25mmの吸音断熱材試料片に対し、厚み方向から直径76mmの圧荷子で0.7Kg/cm2の加重を30分間加え、抜重するというサイクルを24回繰り返した後の厚みを測定し、当初の厚み(25mm)に対する百分率で表示したものである。
更に、ガルバニック電流とは、セルダイアグラムが炭素繊維電極|0.45重量%塩化ナトリウム水溶液|アルミニウム電極で表されるガルバニックセルで測定したときにおける電流値をいう。詳細は後記する。
図面の簡単な説明 図1は、炭素繊維の炭化処理温度とガルバニック電流及び電気腐食の関係を示すグラフである。
図2は、炭素繊維の炭化処理温度と単繊維の引張強度との関係を示すグラフである。
図3は、炭素繊維の炭化処理温度と、この炭素繊維を用いた吸音断熱材の引張強度との関係を示すグラフである。
図4は、炭素繊維(異方性ピッチ及び等方性ピッチ)の炭化処理温度と単繊維の引張強度との関係を示すグラフである。
図5は、炭素繊維(異方性ピッチ及び等方性ピッチ)の炭化処理温度と、この炭素繊維を用いた吸音断熱材の引張強度との関係を示すグラフである。
図6は、炭素繊維の繊維直径と吸音断熱材の熱伝導率との関係を示すグラフである。
図7は、炭素繊維の繊維直径と吸音断熱材の1000Hzにおける垂直入射吸音率との関係を示すグラフである。
図8は、炭素繊維を主構成材料とする吸音断熱材の吸音特性を示すグラフである。
図9は、炭素繊維を主構成材料とする吸音断熱材の嵩密度と断熱性(1/λ)
の関係を示すグラフである。
図10は、炭素繊維を主構成材料とする吸音断熱材の嵩密度と単位嵩密度当たりの断熱性能((1/λ)/ρ)の関係を示すグラフである。
図11は、後記実施例1〜6、比較例1〜2で用いた炭素繊維前駆体の繊維直径の分布図である。
図12は、ガルバニックセルの概略見取り図である。
図13は、電気腐食試験を説明するための説明図である。
図14は、CF製吸音断熱材を構成する炭素繊維相互の接合状態(接合点・)
を示す概念図である。
図15は、引張強度の測定方法(幅方向、長手方向)を説明するための図である。
図16は、引張強度の測定方法(厚み方向)を説明するための図である。
発明を実施するための最良の形態 実験及び実験結果を示す図1〜図13に基づいて、本発明の内容を具体的に説明する。この説明で本発明構成の作用効果が明らかになる。
以下の実験では、特に明示のない限り、平均繊維直径1.3μm(繊維直径0.5μm〜3.5μm)、平均繊維長5mm(繊維長1mm〜15mm)の異方性ピッチを原料とする炭素繊維を使用し、またこの炭素繊維を熱硬化性樹脂で接合してなる嵩密度4.8Kg/m3の吸音断熱材(炭素繊維3次元構造体のみで構成)を使用した。なお、この吸音断熱材の製法等の詳細については後記する。
また、以下では炭素繊維相互の交点を熱硬化性樹脂で接合してなる吸音断熱材を「CF製吸音断熱材」とし、ガラス繊維からなる従来の吸音断熱材をガラス繊維製吸音断熱材(図中ではGF)と称する。
初めに実験方法を説明する。
ガルバニック電流の測定方法 図12にガルバニック電流の測定装置を示す。図12中、1は炭素繊維電極(一方電極)である。この炭素繊維電極1は、炭素繊維自体のガルバニック電流を測定する場合には、炭素繊維100mgを厚み1mm、幅40mm、高さ50mmの集合体となしこれを炭素繊維電極とした。また、CF製吸音断熱材のガルバニック電流を測定する場合には、上記と同サイズに調製したCF製吸音断熱材を炭素繊維電極とした。
2は、厚さ1mm、幅40mm、高さ約50mmのアルミニウム合金2024からなるアルミニウム電極(他方電極)である。3aは、炭素繊維電極1とアルミニウム電極2との距離を規制するために、両電極の間に介在させた0.2mm厚のガラスクロスである。4はガラス板である。このガラス板4は、炭素繊維が脱落しないようにガラスクロス3b(0.2mm厚)を介して炭素繊維電極1の他方面を押さえる役割を担っている。
5は、0.45重量%の塩化ナトリウム水溶液(200ml)からなる電解液である。7は、無抵抗電流計(北斗電工(株)製、HM−104)である。8はガラス製ビーカ(300ml)である。更に、1、2、3a、3b、4からなる電極群9は電解液5に浸漬され、電極1及び2はその上端に取付けられたリード線6を介して無抵抗電流計7に接続されている。
上記のような構造のガルバニック電流測定装置を用い、電解液5に電極群9を浸漬した後、1時間後に電流計7で電流値を読み取り、この電流値をガルバニック電流とした。
電気腐食性の判定方法 図13に示す試験体12を用い電気腐食性の有無を判定した。図13中、10は、縦40mm×横40mm×厚み20mmの大きさに調製した綿状炭素繊維集合体または同様な形状に調製したCF製吸音断熱材からなる試験片である。他方、11は、表面を鏡面状に磨き、更に2%CrO3と2%H3PO4とからなる溶液で表面を処理した縦40mm×横40mm×厚み1mmのアルミ合金2024の板である。12は、試験片10の両側をアルミ合金板11で挟んだ試験体である。
上記試験体12を相対湿度90%、温度40℃の部屋に24時間放置し、24時間後に今度は通常の室内(温度18〜27℃、相対湿度40〜70%)に移し、ここで24時間放置する。そして、24時間後に再び相対湿度90%、温度40℃の部屋に戻すというサイクルを15回(30日間)繰り返した。
15回後(30日後)にアルミニウム鏡面を肉眼観察し、アルミニウム鏡面が当初のままである場合を「電気腐食なし(−)」、アルミニウム鏡面にやや曇りが認められる場合を「電気腐食少しあり(±)」、アルミニウム鏡面が明らかに腐食されている場合を「電気腐食あり(+)」と判定した。
吸音断熱材の引張強度、熱伝導率、垂直入射吸音率、圧縮復元率は、前記した方法により測定した。他方、単繊維の引張強度は、JIS R−7601に従い測定した。この測定方法の詳細は当該箇所に記載する。
次に図に基づいて順次実験結果を説明する。
カルバニック電流と電気腐食の関係 図1は、縮合多環炭化水素を重合した異方性ピッチを平均繊維直径1.3μm、平均繊維長5mmに紡糸し不融化処理した炭素繊維前駆体に対する炭化処理温度と、炭化処理後の炭素繊維又はこの炭素繊維を用い作製したCF製吸音断熱材のガルバニック電流との関係、並びに電気腐食の有無(↑)との関連を示す図である。
図中の●−●は炭素繊維のガルバニック電流を示し、×−×はCF製吸音断熱材のガルバニック電流を示す。なお、図1の横軸(ガルバニック電流)は対数目盛りで示してある。
図1から明らかなごとく、炭化処理温度が上昇すると、ガルバニック電流が指数関数的に大きくなった。他方、「電食の有無」との関連では、ガルバニック電流20μAにおいて電気腐食が若干認められたものの、10μA以下では電気腐食が認められなかった。
これらの結果から、炭素繊維のガルバニック電流を20μA以下とし、より好ましくは10μA以下とすれば、実質的に電気腐食を防止できることが判る。また、横軸と「電食の有無」との対応関係から、電気腐食を生じさせない炭素繊維と成すためには、炭化処理温度を800℃以下、より好ましくは750℃以下とすれば良いことが判る。
ここにおいて、炭素繊維前駆体を十分に炭化するためには、550℃以上の温度を必要とし、550℃未満であると炭化処理が不充分となる恐れがある。このことから、炭化処理温度としては、550℃から800℃以下、より好ましくは750℃以下とするのがよい。
ところで、図1の実験において、炭素繊維のガルバニック電流が20μAにおいて若干の電気腐食が認められたか、上記電気腐食試験は、相対湿度90%、温度40℃の条件を繰り返す過酷な条件での測定結果である。然るに、吸音断熱材の使用条件は通常これほど過酷ではない。したがって、ガルバニック電流を20μA未満とすれば、電気腐食の発生が防止できると考えられる。
また、炭素繊維自体(●−●)のガルバニック電流と、この炭素繊維を用いたCF製吸音断熱材(×−×)のガルバニック電流には若干のズレがあるが、このズレは、CF製吸音断熱材に含まれる熱硬化性樹脂の影響と考えられる。すなわち、熱硬化性樹脂がガルバニック電流を低下させるように作用する。このことから、ガルバニック電流が20μA以下の炭素繊維を使用してCF製吸音断熱材を作製すれば、実質的に電気腐食を生じないCF製吸音断熱材が得られるものと考えられる。但し、上記したごとく、より好ましくはガルバニック電流を10μA以下とするのがよい。
炭化処理温度と引張強度、伸度との関係 図2に炭化処理温度と単繊維の引張強度(Kg/mm2)及び伸度との関係を示す。また、図3上側にCF製吸音断熱材の長手方向の引張強度(g/mm2)
とこのCF製吸音断熱材を組成する炭素繊維の炭化処理温度との関係を示し、図3下側に上記CF製吸音断熱材の圧縮復元率(%)を炭化処理温度との関係を示す。
なお、単繊維の引張強度はJIS R−7601に従い測定した値であるが、繊維直径0.5μm〜3.5μm(平均繊維直径1.3μm)の極細の繊維の引張強度を測定することが困難である。そこで、繊維直径以外の条件を同一として、繊維直径10〜13μmの炭素繊維を作製し、この繊維を用い引張強さを測定し測定結果を単位断面積当たりに換算して示した。また、CF製吸音断熱材は、炭素繊維3次元構造体(嵩密度4.8Kg/m3)のみで構成したものを用い、後記〔引張強度の測定条件〕に記載した条件で測定した値である。
図2から明らかなごとく、炭素繊維自体の引張強度は、炭化処理温度が高くなるに従い一次関数的に大きくなった。これに対し、伸度は、650℃付近に極大値を有していた。また、625℃〜800℃で大きく、800℃以降では変化しないというパターンを示した。
他方、図3から明らかなごとく、CF製吸音断熱材の引張強度は、700℃付近に極大値、800℃付近に極小値を有していた(図3上側)。
また、CF製吸音断熱材の圧縮回復率と炭化処理温度の関係も、上記引張強度曲線と炭化処理温度との関係と同様な挙動を示していた(図3下側)。
これらの結果から、概ね625℃〜800℃の範囲の温度で炭化処理することにより、伸度の大きい炭素繊維が得られ、この炭素繊維を用いてCF製吸音断熱材を作製すると、1.0g/mm2以上の引張強度を有するCF製吸音断熱材となすことができ、このCF製吸音断熱材は圧縮復元率に優れることが判る。
ここで、図2、3において、炭素繊維(単繊維)の引張強度と炭化処理温度との関係が一次関数的であるのに対し、この炭素繊維を用いて作製したCF製吸音断熱材の引張強度と炭化処理温度との関係、及び圧縮復元率と炭化処理温度との関係が、予想に反して極大値と極小値を有する2次関数曲線となったのは、炭素繊維の伸度がCF製吸音断熱材の引張強度や圧縮復元率に大きく影響するためと考えられる。次にこのことを考察する。
図14に、CF製吸音断熱材を構成する炭素繊維相互の接合状態(接合点・)
を示す概念図を示す。図14において、CF製吸音断熱材を矢印方向に引っ張った場合、網目を構成する各線分が引っ張り方向を向くように網目の形状が変化するが、引張方向に対する線分長がそれぞれ異なる。したがって、特定の辺を構成する線分により大きい引張力が掛かるので、その線分が切断されるか、またはその線分を接着している接合点「・」が外れることになる。
ここにおいて、網目が伸度の大きい線分(炭素繊維)で構成されている場合には、特定の辺(線分)により大きい引張力が掛かると、その辺が伸びる結果、他の辺と合力された抗力によって引張力に抗することができるようになる。つまり、網目がネットワークとして抗力できるようになるので、線分の切断や接合点「・」の外れが減少し、全体としての引張強度が大きくなる。そして、このようなネットワークとしての引張強度は、単繊維の伸度と引張強度が好適にバランスしたときに最も大きくなると考えられる。
すなわち、図2、図3の結果は、700℃で炭化処理した場合に単繊維の引張強さと伸びとが最も好適にバランスし、全体としての引張強度(CF製吸音断熱材の引張強度)が大きくなり、またこれによってCF製吸音断熱材の圧縮復元率が高まることを示すものである。
等方ピッチと異方ピッチとの差異 図4に、縮合多環炭化水素を重合した異方性ピッチを原料とする炭素繊維と、石炭タールからなる等方性ピッチを原料とする炭素繊維の炭化処理温度と引張強度の関係をそれぞれ示す。また図5に、これらの炭素繊維で構成したCF製吸音断熱材(嵩密度4.8Kg/m3)について、炭素繊維の炭化処理温度とCF製吸音断熱材の引張強度(長手方向の引張強度)との関係を示す。
図4から明らかなごとく、異方性ピッチを原料とする炭素繊維は、等方性ピッチを原料とする炭素繊維に比べ引張強度が格段に大きかった。また図5から、等方性ピッチを原料とする炭素繊維を用いたCF製吸音断熱材の引張強度は、異方性ピッチの場合におけるような極大値、極小値を有さなかった。この実験結果から、極大、極小値の存在は、縮合多環炭化水素を重合した異方性ピッチを原料とする炭素繊維における特有の特性であるといえる。それゆえ極大、極小値の存在は、本発明にかかるCF製吸音断熱材の性能及び生産効率を高める上で極めて重要な意義を有する。
以上、図1〜図5の実験結果から次のことが結論できる。炭素繊維の伸度(粘り強さ)及びCF製吸音断熱材としたときの引張強度の面から、炭素繊維前駆体としては、縮合多環炭化水素を重合してなる異方性ピッチを原料とするのがよい。また、電気腐食性及び引張強度、伸度の面から、炭素繊維前駆体の炭化処理温度は550℃以上、800℃未満、好ましくは550〜750℃、より好ましくは650℃〜750℃とする。650℃〜750℃で炭化処理した炭素繊維を用いてCF製吸音断熱材を構成すれば、1.0g/mm3以上の引張強度を有し、且つガルバニック電流が10μA以下のCF製吸音断熱材を得られる。このCF製吸音断熱材は、実質的に電気腐食を生じない。
繊維直径と熱伝導率、垂直入射吸音率の関係 図6に、CF製吸音断熱材(嵩密度4.8Kg/m3、厚みは25mm)の熱伝導率λ(W/m・℃)と、当該吸音断熱材を組成する炭素繊維の平均直径との関係を示す。また、図7に同上CF製吸音断熱材の炭素繊維の平均直径と1000HZにおける垂直入射吸音率の関係を示す。更にまた、図6及び図7には、比較基準としてガラス繊維(GF)を用いた従来の吸音断熱材(嵩密度4.8Kg/m2、平均繊維直径1μm、平均繊維長10mm)の熱伝導率または垂直入射吸音率を併記する(プロット×)。
なお、製造された炭素繊維の直径は、図11のように分布するので、ある定まった平均直径のCF製吸音断熱材を製造するのは、製造上種々の工夫及び測定上の手間を要する。よって、図6、図7は、トライアンドエラーにより得た。
図6において、炭素繊維の直径が大きくなるに従い熱伝導率が増加するが、平均直径が5μm以下の炭素繊維を用いたCF製吸音断熱材であれば、平均直径1μmのガラス繊維製吸音断熱材(熱伝導率0.039W/m・℃)と同等以上の断熱性能が得られることが判る。つまり、平均直径5μmの数値限定の内と外では、CF製吸音断熱材が、平均直径1μmのガラス繊維製吸音断熱材と同等以上の断熱性能を保持し得るのか、保持し得ないのかを区別する意義がある。そして、図6において、ガラス繊維の平均直径に比較し、より大きな平均直径の炭素繊維を用いても、ガラス繊維製吸音断熱材よりも良好な断熱性能が得られたという事実は、太い炭素繊維の方が製造容易であることから、予想外の好都合な実験結果であった。
一方、図7から、炭素繊維の平均直径が大きくなるに従い垂直入射吸音率が低下するが、概ね平均直径2μm以下の炭素繊維を用いれば、従来のガラス繊維製吸音材(×)と同等以上の垂直入射吸音率(25mm厚で48%以上)が得られることが判る。つまり、平均直径2μmの数値限定の内と外では、CF製吸音断熱材が、平均直径1μmのガラス繊維製吸音断熱材と同等以上の吸音性能が得られるか、得られないかを区別する意義がある。そして、図7において、ガラス繊維の平均直径に比較し、より大きな平均直径の炭素繊維を用いても、ガラス繊維製吸音断熱材よりも良好な吸音率が得られたという事実は、太い炭素繊維の方が製造容易であることから、予想外の好都合な実験結果であった。
以上から、炭素繊維の平均直径としては、5μm以下、より好ましくは吸音率の点から2μm以下がよいが、平均繊維直径0.5μm未満の炭素繊維を製造することは現在のところむづかしい。よって、炭素繊維の平均直径としては、0.
5μm以上、5μm以下、より好ましくは2μm以下とする。
他方、炭素繊維の長さ(繊維長)については、平均繊維直径0.5μm〜5μmの極細の炭素繊維について15mmを超える平均繊維長のものを製造するのは容易でない。また、15mmを超える長い繊維であると、炭素繊維集合体を作製する際に繊維の向きが2次元的に配向し易いので、好ましくない。一方、平均繊維長1mm未満の短い炭素繊維であると、繊維同志の絡み合いが生じにくいので、良好な3次元構造体を形成できないと共に、構造体から炭素繊維が脱落し易く、脱落した炭素繊維が、例えば周囲にある電気回路内に入り込み電気器機を故障させる等の問題を生じる。
これに対し、3mm〜8mmの平均繊維長であると、製造し易く、また3次元的に配向させ易い。
よって、平均繊維長としては、1mm以上、15mm以下、より好ましくは3mm以上、8mm以下とする。
なお、図8に平均繊維径1.3μmまたは13μmの炭素繊維を用いて作製したCF製吸音断熱材の周波数−垂直入射吸音率曲線を示す。両者の比較から、平均繊維径1.3μmの極細の炭素繊維を用いたCF製吸音断熱材は、特に高周波数領域における吸音性がよいことが判る。
嵩密度と断熱性 嵩密度のみを変化させた種々のCF製吸音断熱材を作製し、これらのCF製吸音断熱材の熱伝導率λ(λ=W/m・℃ ;Wはワット)を測定した。図9に、測定結果を嵩密度と1/λ(断熱性)との関係で表した。この図に基づいて、CF製吸音断熱材の嵩密度と断熱性(1/λ)との関係を説明する。なお、図9には、CF製吸音断熱材(厚みは25mm)における結果(●−●)と、平均繊維直径1.0μmまたは2.5μm、平均繊維長5〜15mmの従来の吸音断熱材(×)の双方が表示してある。
図9から、嵩密度が大きくなるに従い断熱性(1/λ)が良くなるが、その向上程度は嵩密度が大きくなるに従い縮小することが判る。また、同一嵩密度での比較において、CF製吸音断熱材の断熱性がガラス繊維製吸音断熱材よりも遙に優れていることが判る。つまり、CF製吸音断熱材は、ガラス繊維製吸音断熱材よりも軽量なもので同等の断熱性が得られる。更に、嵩密度が3Kg/m3以上のCF製吸音断熱材であれば、平均繊維直径1.0μmのガラス繊維製吸音断熱材と同等乃至それ以上の断熱効果が得られることが判る。
図10に横軸に嵩密度を取り、断熱性(1/λ)を嵩密度ρで除した値((1/λ)/ρ)を縦軸に取った図を示す。この図により吸音断熱材の単位嵩密度当たりの断熱性(重量当たり断熱性能)が明らかになる。すなわち、図10において、嵩密度が大きくなるに従いほぼ直線的に単位嵩密度当たりの断熱性が低下しており、嵩密度が小さいほど重量当たりの断熱性能が良いことが判る。また、CF製吸音断熱材は、ガラス繊維製吸音断熱材(×)に比べ重量当たり断熱性能((1/λ)/ρ)に優れることが判る。
更に、嵩密度10Kg/m3のCF製吸音断熱材の重量当たり断熱性能と、嵩密度6.7Kg/m3のガラス繊維製吸音断熱材(×)の重量当たり断熱性能とが略同等である。この結果から、CF製吸音断熱材の嵩密度を10Kg/m3以下とすれば、少なくとも従来より用いられている代表的な吸音断熱材であるガラス繊維製吸音断熱材(嵩密度6.7Kg/m3)と同等以上の断熱性能が保証できることが判る。
以上から、CF製吸音断熱材の嵩密度としては、好ましくは3Kg/m3以上、10Kg/m3以下とする。
圧縮復元率 圧縮復元率は、CF製吸音断熱材の機械的強度を反映する特性の一つである。
圧縮復元率の小さい吸音断熱材を、例えば振動や振動に伴う圧縮力が作用する条件下で使用した場合、短期間のうちに初期の吸音断熱効果が得られなくなる。なぜなら、圧縮復元率の悪いものであると、振動や圧縮を受けると次第に嵩が小さくなる。嵩が小さくなると内部空隙が減少するので、吸音断熱材自体の性能が低下する。また、嵩の縮小により実装空間に隙間ができるからである。
ここで、本発明の目的の一つは、従来品であるガラス繊維製吸音断熱材と同等以上の性能を有するCF製吸音断熱材を提供することにある。よって、少なくともガラス繊維製吸音断熱材と同程度の圧縮復元率が確保されねばならない。従来より用いられている代表的なガラス繊維製吸音断熱材(嵩密度6.7Kg/m3)の圧縮復元率は、70%である(後記表4の比較例4参照)。
よって、CF製吸音断熱材の圧縮復元率としては、少なくとも70%以上が好ましく、より好ましくは85%以上とする。圧縮復元率が85%以上であれば製造時や実装時における外力に耐えることができ、恒常的に振動や圧縮力がかかる状況でも使用可能だからである。
3軸方向の引張強度比率 本発明のCF製吸音断熱材の更なる限定要素を説明する。本発明は、極細の炭素繊維を用い軽量で高性能なCF製吸音断熱材の提供を目的とし、かつ高速鉄道車両や航空機などにおけるような恒常的に振動や圧縮力がかかる用途で使用可能なものを提供しようとするが、極細の繊維を用い、嵩密度の小さいCF製吸音断熱材を作製した場合、中太の繊維を用いた嵩密度の大きなものに比べ、機械的強度が小さくなる。このため、取扱性、施工性、耐久性に劣ものとなり易い。
特に、縦方向、横方向、厚み方向の3方向の強度に極端に差があると、強度の弱い方向から崩壊し易いが、極細の繊維を用い且つ嵩密度の小さいものとする以上、各方向の絶対的強度をそれ程大きくすることにはできない。よって、軽量で嵩密度が小さく、しかも取扱性、施工性、耐久性、圧縮復元率に優れたCF製吸音断熱材と成すためにには、3次元座標におけるX、Y、Z軸(以下、3軸という)の各方向の引張強度の差を小さくする必要がある。
以上から、本発明の好ましい形態としては、吸音断熱材の最大引張強度方向に直交する方向における最小引張強度を前記最大引張強度の4%以上とし、前記最大引張強度方向と前記最小引張強度の方向の双方に直交する方向の引張強度を前記最大引張強度の35%以上とする。
以下、この数値の根拠を表1、表2に基づいて説明する。表1は、嵩密度のみを変えた吸音断熱材について、長手方向、幅方向、厚み方向の3軸の各方向から引張強度を測定した結果である。表2に、最大引張強度方向の引張強度に対する最少引張強度方向の引張強度及び中間引張強度方向の引張強度の比率、並びに中間引張強度方向の引張強度に対する最少引張強度方向の引張強度の比率(百分率で表示)を示す。
なお、通常、最少引張強度方向は厚み方向であり、最大引張強度は長手方向又は幅方向となる。また、中間引張強度方向とは、最大引張強度と最少引張強度の中間に位置する引張強度の方向であり、通常では幅方向が中間引張強度方向となる。
〔引張強度の測定条件〕
定速緊張型引張試験機を用い、次の条件で測定した。
(1)幅方向、長手方向の引張強度 引張スピード ;20mm/min スパン(試料長) ;50mm 試料サイズ ;縦横50mm、厚み25mm(図15参照)
(2)厚み方向の引張強度 引張スピード ;20mm/min スパン(厚み) ;25mm 試料サイズ ;縦横60mm、厚み25mm(図16参照)
ここで、厚み方向の引張強度は、CF製吸音断熱材の両面(図16の引張しろ部分)に板を張りつけ、この板を矢印方向に引っ張る方法により測定した。比較対象としたガラス繊維製吸音断熱材は、平均繊維直径1μm、平均繊維長10mmのガラス繊維からなるものである。
表1 で明らかとなるように、同一の嵩密度で比較した場合、CF製吸音断熱材の方がガラス繊維製吸音断熱材よりも大きな引張強度であった。特に両者の幅方向及び厚み方向の引張強度に大きな差が認められた。具体的には、CF製吸音断熱材の厚み方向の引張強度方向は、嵩密度5Kg/m3でガラス繊維製吸音断熱材の8.5倍であり、嵩密度10Kg/m3でガラス繊維製吸音断熱材の15倍であった。
他方、表2において、最少/最大、中間/最大、最少/中間の各引張強度比率(百分率)を同一嵩密度で比較した場合、CF製吸音断熱材の方が、ガラス繊維製吸音断熱材(従来品)よりも各数値が大きく、それだけ各軸方向の引張強度に差が少ないことが判る。特にCF製吸音断熱材の長手方向と幅方向の差が極めて小さいことが判る。具体的には、CF製吸音断熱材の中間引張強度方向/最大引張強度方向の比率は、嵩密度3Kg/m3〜10Kg/m3において、86%以上であった。また、最少引張強度方向/最大引張強度方向の比率は、嵩密度3Kg/m3〜7Kg/m3において、5.4以上であった。
ところで、吸音断熱材の製造時や実装時における取扱性や耐久性等を考慮すると、3軸の各方向の引張強度差が小さいほどよいが、製造上の理由から引張強度差を無くすことは困難である。なぜなら、炭素繊維を堆積して綿状の炭素繊維集合体を作製する製法を採用した場合、堆積に際して繊維が重力に対しより安定な配向状態になろうとするので、堆積物を組成する繊維の多くは重力と直交する方向に配向する。つまり、長手方向又は幅方向に配向し易いので、このような配向状態の繊維を接合してなる吸音断熱材では、長手方向又は幅方向の引張強度が過大になり、厚み方向の引張強度が過少になる傾向がある。
但し、CF製吸音断熱材の引張強度差が従来品以下であれば、少なくとも従来品と同等以上の取扱性、耐久性が確保できることになる。すなわち、前記表2からして、最少/最大の比率を4%以上とし、中間/最大の比率を35%以上とすれば、従来品と同等以上の取扱性、施工性、耐久性が確保できる。そして、前記表2の結果から、嵩密度が3Kg/m3〜7Kg/m3のCF製吸音断熱材であれば、この条件を満たすことができる。
次に、以上で述べてきた諸物性を具備するCF製吸音断熱材の作製方法について説明する。
先ず、公知の方法(特開昭63−146920公報)で縮合多環炭化水素を重合した異方性ピッチを作製する。次いで、このピッチを加熱溶融し、紡糸ノズルから吐出させ、同時に紡糸ノズルの周囲から加熱ガスを前記吐出方向と同じ方向(好ましくは吐出方向と平行方向)に噴出させて紡糸繊維を作製する。この加熱ガスは吐出物が直ちに冷却するのを防止し、かつ適当な長さの繊維を得る役割を担っている。
上記の紡糸繊維は、例えばネットで補集し、不融化処理(酸化処理)を施す。
これにより炭素繊維前駆体を作製できる。この炭素繊維前駆体を、不活性ガス中で650℃〜750℃の温度で炭化処理して、炭素繊維となす。
上記製法において、紡糸ノズルの吐出口の直径を0.5mm〜0.2mmの範囲で可変し、またピッチの加熱溶融温度及び吐出速度、並びに加熱ガスの温度、噴出速度を調節することにより、紡糸繊維の平均直径や平均繊維長を任意に変化させることができる。
なお、不融化処理や炭化処理により若干繊維径や繊維長が変化するが、測定誤差を考慮した場合、紡糸繊維のサイズと炭素繊維のサイズに実質的な差がなく、平均繊維径、平均繊維長にも実質的に差が生じない。
上記炭素繊維を用い次のようにして本発明にかかるCF製吸音断熱材を作製する。
先ず、ネット等で補集した炭素繊維を、空気を吹きつける方法等で開繊し、これを落下させ熱硬化性樹脂液を噴霧しながら堆積する方法(噴霧堆積法)、または、開繊した炭素繊維を平面状に落下し堆積して粗な綿状の集合体を形成し、この集合体に熱硬化性樹脂液を噴霧する方法(堆積−噴霧法)で、熱硬化性樹脂の噴霧した炭素繊維集合体(噴霧堆積物)を作製する。
次に、前記噴霧堆積物に対し、通常、厚み方向から2枚の押圧板で軽く圧縮し、この状態で加熱して熱硬化性樹脂を硬化する。これにより、炭素繊維相互の交点が熱硬化性樹脂で接着された炭素繊維3次元構造体が形成される。なお、厚み方向と直交する方向から押圧板を当てがってもよい。
ここで、本発明にかかるCF製吸音断熱材は、上記炭素繊維と熱硬化性樹脂のみから組成されるものであってもよく、また上記炭素繊維を主材としてこれに吸音断熱性を損なわない範囲で他の繊維を含めたものであってもよい。このような繊維としては、例えばガラス繊維、ポリエステル繊維、セラミックス繊維などが例示できる。
上記製法をより具体的に説明すると、熱硬化性樹脂の添加量をbKg/m3とした場合、例えば少なくとも炭素繊維集合体の嵩密度を(3−b)Kg/m3以上、(10−b)Kg/m3未満とすることにより、3Kg/m3以上で10Kg/m3未満のCF製吸音断熱材とすることができる。
この場合、好ましくは炭素繊維集合体の嵩密度(bを除く嵩密度)を1.3Kg/m3未満として、加熱成形に際し上記2枚の押圧板の間隔を調整して所望の嵩密度の成形物(炭素繊維3次元構造体)と成すのがよい。なぜなら、1.3Kg/m3未満の粗な嵩密度の集合体とした場合、繊維が十分にランダムに配向する。よって、繊維相互の交点のみが接着された嵩高い(嵩密度の小さい)炭素繊維3次元構造体が得られ、このような構造体であると、3軸の各方向の引張強度がより均一になる。
また、上記噴霧堆積物の作製においては、好ましくは開繊した炭素繊維を100cmの高さから平面上に落下させるのがよい。この方法であると特別な装置を用いることなく、繊維をランダム配向できる。なぜなら、平均繊維直径0.5μm〜2μm、平均繊維長3mm〜8mmの軽量な炭素繊維であると、100cmの高さから落下させた場合、空気抵抗により、あるものは重力方向に配向し、またあるものは重力方向と直交する方向に配向するからである。つまり、無秩序な方向に配向した嵩高い炭素繊維の堆積物(綿状繊維集合体)が得られる。よって、この堆積物に熱硬化性樹脂液を噴霧すれば、ランダム配向した炭素繊維3次元構造体が得られる。
炭素繊維を落下させる方法としては、自然落下させてもよく、また落下に際して下方向(落下速度を減じる方向)または上方向(落下速度を増す方向)から空気流を作用させるのもよい。空気流を作用させる方法であると、繊維の配向を制御できるので、所望の嵩密度の繊維集合体が作製し易い。
なお、通常、雪を降らすようにして平面上に少しづつ自然落下させた場合、炭素繊維の個々は3軸の各方向にかなりランダンム配向する。しかし、それでも重力と平行な方向(長手方向又は幅方向)に配向する炭素繊維が多くなるので、長手方向又は幅方向に比較し厚み方向の引張強度が小さくなる傾向がある。このため、特別に厚み方向の引張強度を大きくしたいような場合には、プレス機でのプレスにおいて、長手方向および/または幅方向から圧縮する方法を採用するのもよい。この方向からの加圧であると、3軸方向の引張強度に大きな差のないものができる。
上記で使用する熱硬化性樹脂としては、例えばフェノール樹脂、メラミン樹脂、シリコーン樹脂が使用できる。また、その使用量としては、通常、CF製吸音断熱材に対し10〜40重量%、好ましくは20〜30重量%とする。40重量%を超えるとバインダー量が多すきるため、炭素繊維相互の交点以外をも接着するので好ましくない。その一方、10重量%未満であると、前記交点を十分に接着できないので、引張強度および圧縮復元率が過小になるからである。
更に、フェノール樹脂の上記加熱成形時の加熱温度としては、150℃〜250℃とし、通常では180℃〜220℃とする。
以上のような製法により、前記した諸物性を有する本発明のCF製吸音断熱材を得ることができる。
本発明を実施例に基づいて更に具体的に説明する。
〔実施例1〜4〕
縮合多環炭化水素を重合して得た軟化点280℃のピッチを320℃で溶融し、直径0.25mmの吐出孔を有する紡糸ノズルから溶融ピッチを吐出するとともに、吐出孔の周囲から320℃の加熱気体を、前記溶融ピッチの吐出方向と同じ方向でかつ吐出方向と平行に吹き出しながら紡糸し繊維化してネットで補集した。この炭素繊維前駆体の直径は約0.5〜3.5μm(平均繊維直径1.3μm)、繊維長は1〜15mm(平均繊維長5mm)であった。図11にこの条件で作製した炭素繊維の直径分布を示す。
次いでこの繊維を空気雰囲気で300℃、30分間加熱し不融化処理した後、所定温度(650℃、700℃、750℃、800℃)の不活性ガス雰囲気中で30分間加熱する方法で炭化処理した。このようにして炭化処理温度の異なる4通りの炭素繊維を得た。これらの炭素繊維の直径及び繊維長は概ね上記炭素繊維前駆体と同様であった。
上記4通りの炭素繊維をそれぞれ用いて4通りのCF製吸音断熱材を作製した。具体的には、繊維相互が絡み合った炭素繊維に空気を吹きつけて開繊し、開繊した炭素繊維を100cmの高さから雪を降らすようにして少しづつ平面上に自然落下させて、厚さ120mm、嵩密度約0.7Kg/m3の綿状の集合体(未結着状態)を作製した。
次いで、この炭素繊維集合体に20wt%のフェノール樹脂溶液を炭素繊維集合体に対し150重量%噴霧し、2枚の押圧板を備えるプレス機で厚さ約25mmまで圧縮し(縦、横方向は圧縮せず)、この状態で200℃に加熱しフェノール樹脂を完全に硬化させた。このようにして、縦1.5m、横0.5m、厚み25mm、嵩密度4.8Kg/m3の炭素繊維3次元構造体(4通り)を作製し、これをCF製吸音断熱材とした。
〔実施例5〕
炭化処理温度を700℃としたこと、及び炭素繊維集合体の厚みを100mmとしたこと以外については、前記実施例1〜4と同様にして、嵩密度4.0Kg/m3の実施例5のCF製吸音断熱材を作製した。なお、サイズ、厚みは前記実施例1〜4と同様である。
〔実施例6〕
炭化処理温度を700℃としたこと、及び炭素繊維集合体の厚みを175mmとしたこと以外については、前記実施例1〜4と同様にして、嵩密度7.0Kg/m3の実施例6のCF製吸音断熱材を作製した。サイズ、厚みは前記実施例1〜4と同様である。
〔比較例1〕
炭化処理温度を850℃としたこと以外については、前記実施例1〜4と同様にして、比較例1のCF製吸音断熱材を作製した。なお、サイズ、厚み、嵩密度については、前記実施例1〜4と同様である。
〔比較例2〕
炭化処理温度を900℃としたこと以外については、前記実施例1〜4と同様にして、比較例2のCF製吸音断熱材を作製した。サイズ、厚み、嵩密度については、前記実施例1〜4と同様である。
〔比較例3〕
石炭系等方性ピッチを原料とし且つ950℃で炭化処理した繊維直径13μm、平均繊維長25mmの炭素繊維を用いたこと以外は、実施例1〜4と同様の方法で、比較例3にかかる吸音断熱吸音材を作製した。
〔比較例4〕
平均繊維直径1.0μm、平均繊維長10mmのガラス繊維同志をフェノール樹脂で接合したガラス繊維製吸音断熱材(厚み25mm、嵩密度6.7Kg/m3)を比較例4とした。
実施例1〜6、及び比較例1〜4の各種吸音断熱材についても実施の形態で記載した方法と同様な試験を行った。その試験結果を炭素繊維の製造条件と共に表3、表4に一覧表示する。
表3から明らかなごとく、実施例1〜6はガルバニック電流が0.2μA〜17μAであり、ガルバニック電流が17μAの実施例1で電気腐食が極僅かに認められたものの、実施例2〜6では全く電気腐食が認められなかった。
これに対し比較例1(炭化処理温度850℃、ガルバニック電流56μA)、比較例2(炭化処理温度900℃、ガルバニック電流110μA)、比較例3(炭化処理温度950℃、ガルバニック電流36μA)
では電気腐食が認められた。なお、比較例4で電気腐食が認められなかったのは、ガラス繊維はガルバニック電流を生じないからである。
表4において、本発明にかかる実施例1〜6の引張強度比率(百分率)は、P2/P1=82〜100、P3/P1=5.0〜6.3であった。これに対し、比較例4ではP2/P1=33、P3/P1=2.5であり、本発明のCF製吸音断熱材に比較し3軸の各方向の引張強度差が顕著に大きかった。
また、熱伝導率(W/m・℃)は、嵩密度4.8Kg/m3の実施例1〜4が0.035〜0.037、嵩密度4.0Kg/m3の実施例5が0.037、嵩密度7.0Kg/m3の実施例6が0.033であった。これに対し、嵩密度6.7Kg/m3の比較例4(ガラス繊維製吸音断熱材)の熱伝導率は0.039であった。この結果から、本発明にかかるCF製吸音断熱材は、ガラス繊維製吸音断熱材に比べ小さい嵩密度で、より高い断熱性能が得られることが実証された。なお、熱伝導率の大小と断熱性能の良否とは逆の関係にある。
更に、25mm厚における1000HZ垂直入射吸音率(%)は、嵩密度4.
8Kg/m3の実施例1〜4が52〜55、嵩密度4.0Kg/m3の実施例5が50、嵩密度7.0Kg/m3の実施例6が60であった。これに対し、嵩密度6.7Kg/m3の比較例4(ガラス繊維製吸音断熱材)の25mm厚における1000HZ垂直入射吸音率(%)は48であった。この結果から、上記と同様、本発明にかかるCF製吸音断熱材は、ガラス繊維製吸音断熱材に比べ、小さい嵩密度でより優れた防音効果が得られることが実証できた。
産業上の利用可能性 以上に説明したように、本発明構成によれば、本発明の各課題を十分に達成することができる。すなわち、優れた断熱性、吸音性に加え、引張強度や圧縮復元性にも優れた吸音断熱材が実現できる。また、本発明の吸音断熱材は、炭素繊維を主構成材料とするものであるので、炭素繊維が備える好適な特性、即ち軽量性、化学的安定性、難燃性、火災時において有毒ガスを発生しない性質、吸湿しにくい性質をも兼ね備えている。更に本発明の吸音断熱材は、炭素繊維からなる吸音断熱材の弱点である電気腐食性や非導電特性が改善してあり、さらに引張強度や圧縮復元率等の機械的特性も格段に向上させてある。
このような吸音断熱材であると、実装当初における吸音断熱性能が優れることは勿論のこと、長期間の使用によっても吸音断熱性能が劣化しない。また、吸音断熱材が実装された周囲の部材を電気腐食しない。加えて、吸音断熱材本体や本体から脱落した繊維が電気回路をショートさせる恐れもない。
よって、本発明によれば、住宅等の省エネルギー化を実現する部材として使用できることは勿論、恒常的な振動が存在し、かつ金属素材が多く用いられ、更に多様な電気機器が搭載された例えば航空機、高速鉄道車両、宇宙船等においても好適に使用できるCF製吸音断熱材が提供できる。よって、本発明の産業上の意義は大である。