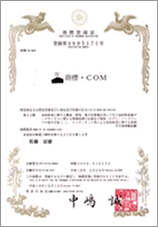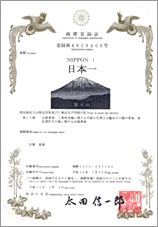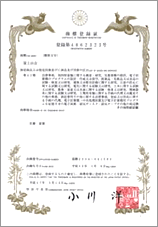先願特許発明と後願特許発明との利用抵触関係について
−先願特許権者は後願特許発明を事由に実施できるか?−
先願特許発明と後願特許発明との利用抵触関係について
―先願特許権者は後願特許発明を自由に実施できるか?―
特許事務所 富士山会 代表者 弁理士・行政書士 佐藤富徳
抄録
我国の特許法では、先願特許発明と後願特許発明との利用関係1)について規定している(特許法第72条)が、抵触関係2)については法上有り得ないとして規定されていない。
しかし、選択発明、用途限定の発明等の場合、実際に実施する上で不可避的に抵触関係を生じる場合がある。
そこで、このような場合について例を挙げて説明するとともに、どのように権利調整をしたら良いかについて論じることとした。
なお、我国では、特許権は本来的に専用権と排他権の両方有すると考えること(両権説として提起する。)により、国際的に広く認められている排他権説とを対比しつつ、我国の特許法の問題点等にも触れることとした。
目次
1.はじめに
2.専用権説と排他権説と両権説
2.1専用権説
2.2排他権説
2.3両権説
2.4各説の比較
3.利用抵触関係について
3.1外的付加発明の場合
3.2実施態様発明の場合
3.3利用抵触関係にない場合(いわゆる穴空き特許)
3.4選択発明の場合
3.5数値限定発明の場合
3.6用途限定発明の場合
3.7ファンクショナルクレームの場合
3.8マーカッシュ形式の場合
4.利用抵触関係の場合の取扱い
4.1外的付加の利用関係について
4.2内的付加等による抵触関係について
4.3穴空き特許の場合
4.4その他
5.諸外国との比較
5.1米国との比較
5.2欧州との比較
5.3条約との関係
6.結論
7.おわりに
1.はじめに
弁理士は単に産婆役であるとすれば、発明が誕生した後出願をして特許権を取得すればそれで御役御免ということになる。しかし、それだけでは弁理士のもう一つの重要な業務となろうとしている鑑定書、見解書は書けないし、クライアントから真に信頼を得ることもないであろう。特許は、熾烈な競争下にある企業の経営資源として認知されており、特許後において、どのように取得特許が取扱われるかということを熟知することは非常に重要であろう。このことが特許権のダイナミックな活用に繋がるのではなかろうか?これに応えるためには、先願特許発明と後願特許発明との利用抵触関係について論ずる必要がある。特許発明の利用抵触関係は企業側が改良発明を絶えず次から次へと行なうことによって生ずる。改良発明は、先願特許発明A+Bに構成要件Cを付加して、後願特許発明A+B+Cとすることによって生じ、付加には外的付加3)と内的付加4)がある。外的付加の場合には利用関係が、内的付加の場合には抵触関係が生じ易いことを具体例を挙げて指摘することとする。
このような先願特許発明A+Bと後願特許発明A+B+Cとの利用抵触関係について、先願特許権者は後願特許発明A+B+Cを自由に実施できるか否かについても論ずることとする。
2.専用権説と排他権説と両権説
2.1専用権説5)
我国の利用関係の取扱いについては、一般には通説である専用権説に基いて説明されている。利用関係については、専用権同士の権利調整をするという考え方である。6)専用権説の基本的考え方は特許権者のみが特許発明について自己のみが実施できる権利(専用権)を専有する(自己のみが有する7))という我国の特許法第68条からきている。基本的には、特許権者は自己の特許発明を自由に実施できるが、唯一の例外は利用抵触関係にあれば、後願特許権者は先願特許発明等を自由に実施できないと説明するものである。その他については、調整規定がないので原則として自由に実施できるというものであろう。専用権説の立場を採る者としては吉田清彦、吉藤幸朔がいる。
2.2排他権説8)
特許権の本質は、排他権であるとして、特許法の条文解釈を行なう立場であり、専用権説では特許法第72条の必須の調整規定であるのに対して、他排他権説では確認的規定である。排他権説は企業側の本音部分をズバリと言っているので歯切れが良くて調整規定すら設ける必要がなく非常に単純明快である。外国においては、排他権説に則った特許法が規定されており、この説の追い風となっている。この排他権説としては、竹田和彦、三宅正雄、野一色勲9)がいる。
2.3両権説
ここで、私は、特許権の本質は一の権利だけではなく、素粒子の超紐理論10)とも通じるように、特許権は、専用権と排他権の二つの性質を本来的に有するものであると考えた方が歴史的にも、かつ現行法を理解し易いしかつ合理的であると考える。
歴史的には、特許法がない時代には発明は現在のノウハウと同様に取扱われていた。特許法による保護の時代に入ると、ノウハウの実施権としての保護は、より強大な専用権としての保護に格上げされ、さらに、専用権の実質的保護を担保すべく排他権を立法的に創設したものである。専用権はいざ知らず、特に排他権は、実質的に存在していたものを法が後追いで追認したような権利とは異なるのである。専用権説は専用権同士の調整という立場に立つのであるが、両権説では、利用関係の調整は、先願特許権者の排他権と後願特許権者の専用権との調整が必要となるのであり、公平の観点に立って、かつ法目的に照らして権利調整をする必要があろう。特許権には、盾と矛の両面が有り、特許法72条の権利調整では先願特許権者の矛が後願特許権者の盾を貫く図式をイメージすれば、理解が容易となろう。以下、特に断らない限り両権説に立って主として説明していくことにする。
2.4各説の比較
専用権説と排他権説については、特許権との本質は一つの権利に帰着することを前提としているが、これは必ずしも正しくはない。特許権の本質は専用権と排他権の両方の権利を併せ持つことが本質であると考えても何ら問題ないからである。
我国の特許法の利用関係の規定(特許法第72条)は、専用権説に立っても排他権説に立っても、単に解釈だけで、どちらの立場に立っても利用関係の調整では同じ結論が得られよう。
調整規定のない過誤特許の場合/あるいは同日に係る場合は問題となり、両説どちらの立場に立つかで結論は全く逆になる。例えば、排他権説に立てば、先願特許権者は後願特許発明A+B+Cを実施できないこととなるが、専用権説に立てば、例外規定がない以上、両者とも実施できるか/あるいは一方のみが実施できるかの何れかであろう。
両権説に立てばどうなるのであろう。必ずしも、簡単には行かないのである。先願特許権者は先願特許発明A+Bの専用権を有し、後願特許権者は後願特許発明A+B+Cの排他権を有しているのであり、専用権説と排他権説の難点を無理なく説明できるので優れた説であると自負している。なお、両権説では、後願特許権の排他権と先願権利の専用権のどちらを優先させるかの盾矛の強弱論に辿り着くということに留意すべきであろう。
3.利用抵触関係について
特許発明の利用関係は、企業同士の競争において絶えず改良発明をする過程の中で生じてくる。改良発明は、外的付加発明と内的付加発明に大きく分類されよう。内的付加発明の代表的なものは選択発明であり、選択発明には数値限定発明、用途限定発明等が挙げられよう。内的付加発明は、さらに抵触関係を生じさせる場合もあり複雑化する。以下、利用抵触関係について具体的に述べることとする。
3.1外的付加発明の場合
ここに、外的付加とは、先願特許発明A+Bと上位概念・下位概念の関係にない構成要件Cを付加して後願特許発明A+B+Cとすることをいう。
例えば、故吉藤幸朔先生も例に揚げているように、学習机についてカレンダーを付加した場合をいう。外的付加の場合には、内的付加(選択発明)と違って、構成要件Cが先願特許発明A+Bとは上位概念・下位概念の関係にないから、先願特許発明A+Bを実施しても、後願特許発明A+B+Cを実施することにならない。逆に後願特許発明A+B+Cを実施すれば、先願特許発明A+Bを実施することになる(実施不可避説))。この結論については、専用権説、排他権説いずれの説に従っても、同じ結論に達することになる。
3.2実施態様発明の場合
実施態様発明とは、先願特許発明がA+Bであるが、後願特許発明A+B+Cが、先願特許発明A+Bの実施態様発明である場合をいう。
例えば、Cが記載されている場合、あるいは、具体的には記載されていないが、実施態様発明A+B+Cが当業者知識を参酌すれば記載されているに等しい場合は、先願特許発明A+Bと後願特許発明A+B+Cとは同一発明であり、一方の権利内容を実施すれば他方の権利内容を実施する関係に有り、いわゆる抵触関係に有ると言えよう。
このような場合、後願特許権は過誤特許であり、特許法第39条あるいは特許法第29条の2の無効理由を有することとなる。このような抵触関係の場合は、法が予定していないとして調整規定を設けていないので問題となり、どのように取扱うべきであるかについては後述することとする。
3.3利用関係のない場合(いわゆる穴空き特許)
先願特許発明が選択発明の場合、未完成発明だから特許になったのであり先願特許権には元々穴が空いているのだから、先願特許発明と後願特許発明は別発明であり、利用関係がないという説がある。(いわゆる穴空き説11))ただし、選択発明を特許することは、実務上広く認められており、全ての場合について穴空き特許であるとして利用関係を否定し、先願特許権者、後願特許権者双方とも自由に実施できるといういわゆる穴空き説は斥けられるべきであろう。
一見後願特許発明A+B+Cを実施すれば、先願特許発明A+Bを実施するように形式的には見えるが、実際にはCなる条件を付加することによって後願特許発明A+B+Cは先願特許発明A+Bとは全くメカニズムが相異する場合、先願特許発明A+Bと後願特許発明A+B+Cとの間に利用関係はない。12)全ての先願特許権に穴が空いているとする極端な穴空き説は斥けられるが、穴が空いている“穴空き先願特許権”は、上例に見られるように実在するであろう。それでは、どのような場合に先願特許権に穴が空いているのであろうか?これを見極めることは、熾烈な競争下にある企業にとって特に重要である。先願特許発明はA+Bであるので、一つには、構成要件がどこまで開示されているかに掛かってくる。A、Bの構成要件が非常に深いところまで開示されているとすれば、権利範囲が実質的に広くなり、中が詰まった実の有る特許(スカスカのがらんどうの特許(いわゆる穴空き特許)ではない特許)を取得できよう。構成要件の概念は非常に重要であるが、全てを記載することは至難の技であろう。現在の実務では、広いクレームであっても、実施例は一つ有ればあるいは無くても、特許を取得することができる。従って、広いクレームの特許取得を心掛けることは、絶対に間違いのない戦略の一つということができよう。特許無効にさえされなければ、特許法第72条という先願特許権者の有利な立場を主張できるであろう。気を付けなければならないのは、先願特許権の範囲外すなわち穴の空いた個所にあつたベストモード発明を後願者に特許として取られてしまえば、最早先願特許権者にとって優位な立場がぐらついていることになろう。この様な穴空き特許を防止するためには、言葉の持つ概念の範囲がどこまでかを常日頃から感覚的に把握する以外にないであろう。(図1を参照)
後は、実際に、後発メーカーとして出願する際に先願特許権者の矛先を掻い潜って特許権を取得するという“後の先”を取るという、言わば“後の先”を取るように心掛けるしか良策はないではなかろうか?後の先が簡単に取れるのであれば、特許に携わる者として、苦労することもないし、逆に言えば、“後の先”を取ったと喜びすら半減するではなかろうか?
3.4選択発明の場合
選択発明とは、上位概念発明について、さらに具体的に限定条件Cを加えて下位概念とした発明をいう。選択発明は、内的付加の発明の代表的なものであろう。
上位概念発明をA+Bとし、限定要件Cを付加することによって、A+B1とした場合、後願特許発明A+B+C(以下、選択発明を論ずる場合には、A+B1とも表示する。)は上位概念発明A+Bの中に入っているようにも一見考えられる。
第1の問題点として、先願特許発明A+Bと後願特許発明A+B1とがどのような関係にあるか?ということである。具体例に基いて議論しよう。Cなる特徴的限定条件を付加した後願特許発明A+B1が先願特許発明A+Bとは、同質な効果を有するが異質な効果も有する場合、あるいは同質な効果も有するがさらに顕著な効果を有する場合、後願特許権者が後願特許発明A+B1を実施すれば、先願特許発明A+BのA+B1部分すなわち先願特許発明A+B1を実施することになり、逆に、先願特許権者が先願特許発明A+B1を実施すれば、後願特許権発明A+B1を実施するといういわゆる抵触関係にあるということができよう。先願特許明細書にも、後願特許発明A+B1の構成及び同質の効果(ただし、異質の効果、同質の効果であるが顕著な効果については開示されていない。)について開示されているからである。
なお、故吉藤幸朔先生も、選択発明の代表として有名な混血動物に対して毒性の極めて少ない殺虫剤(特公昭39−17191)と有機燐酸エステルの製法(特公昭26−6170)の場合(有機燐酸エステルは、殺虫剤の一般式に該当している。)を例に採り上げて、「上例のように、先行発明の効果をそのまま有し、かつ、プラスの効果を奏する場合においてもなお、選択発明は利用発明でないとすることは、不当に基礎発明の保護を制限するものである。」と論じている。13)しかし、残念ながら、さらに一歩踏み込んで先願特許発明A+B1の範囲について利用関係ではなく抵触関係を生じる場合が有るというところまでは論じられていない。
第2の問題点として、後願特許発明の進歩性のレベルが落ちてきて、先願特許発明A+Bに対して、Cなる限定要件を加えて、機能・作用(メカニズム)が異なるため非同一となる関係の場合(例えば、具体的には、審査基準14)を参照のこと。)については、どのように考えたら良いのであろうか?このような場合、後願特許権が成立するのは、先願発明が公開になる前に、後願発明が出願されて、後願が特許法第29条の2、特許法第39条をクリアして特許された場合のみが、議論の対象となるのである。その他の場合は過誤特許となるからである。
3.5数値限定発明の場合
数値限定物の発明15)は、選択発明の一種と考えることができ、選択発明の場合とほぼ同様に論ずることができよう。構成要件である数値限定を施すことにより、数値限定物の性能(効果)が数段アップした場合、どのように考えたら良いであろうか?
先願特許明細書には、Cなる数値限定をすれば後願特許発明の顕著な効果あるいは異質の効果を発揮することについての具体的開示はないが、後願特許明細書には、Cなる数値限定を付加することによって、先願特許明細書に記載されているより、同質の効果であるが顕著な効果、同質の効果も発揮するが異質の効果も発揮する場合(すなわちCの付加により進歩性をクリアする要件である場合)は、両方発明とも特許を附与され得る。このような場合、後願特許権者が後願特許発明A+B1を実施すれば、先願特許発明A+B1を実施することになり、逆に、先願特許権者が先願特許発明A+B1を実施すれば、後願特許権発明A+B1を実施するといういわゆる抵触関係にあるということができよう。
なお、後願特許発明が、先願特許発明に対して単に非同一すなわち特許法第29条の2、特許法第39条をクリアして特許された場合(審査基準を参照16))も、選択発明の場合で論じたごとく、特許法では予定されていない特許権同士の抵触関係にあるということができよう。
3.6用途限定発明の場合
用途限定発明も、選択発明の一種として把握することができよう。我国では米国と異なって、用途限定物の発明17)を特許しており、用途限定物の発明は、熾烈な競合関係にある企業にとって、特許要件のみではなく成立した特許の効力範囲についても見極めることは重要である。この場合も、Cなる用途を限定することを言っているのであり、A+Bなる物について異質の効果を発見して、後願特許発明A+B+Cなる用途限定物の発明をしたものである。A+Bが活性炭浄水器フィルターの発明であり、ここにBは活性炭の細孔分布の数値限定であり、塩素除去の効果があると特許明細書に記載されていたとしよう。A+Bなる活性炭浄水器フィルターの発明を利用して、トリハロメタン除去に特に優れた効果を有することを発見して、Cをトリハロメタン除去用の活性炭浄水器フィルターとして後願特許権が成立した場合を論じよう。
この場合、先願特許権者は、自己の特許発明であるBなる細孔分布の数値限定をした活性炭浄水器フィルターA+Bを実施すれば、後願特許発明であるBなる活性炭の細孔分布の数値限定をしたトリハロメタン除去用の活性炭浄水器フィルターA+B+Cを実施することになり、後願特許権者も、後願特許発明A+B+Cを実施すれば先願特許発明A+Bを不可避的に実施することになり、両特許発明は抵触関係にあるということができよう。なぜならば、先願特許権者は、自己の先願特許発明A+Bを実施すれば、不可避的にトリハロメタン除去用の効果をも奏することになるからである。
次に、先願特許権者の発明が、後願特許発明A+B+C0、後願特許発明が、後願特許発明A+B+Cであった場合において、A+Bは、Bなる活性炭の細孔分布の数値限定をした活性炭浄水器フィルターであって、C0が塩素除去用の用途限定、Cがトリハロメタン除去用の用途限定をしたものである。すなわち、先願特許発明A+B+C0が、Bなる活性炭の細孔分布の数値限定をした塩素除去用の活性炭浄水器フィルターの発明であり、後願特許発明A+B+Cが、Bなる活性炭の細孔分布の数値限定をしたトリハロメタン除去用の活性炭浄水器フィルターである場合について考えよう。
この場合、先願特許権者は、自己の活性炭浄水器フィルター後願特許発明A+B+C0を実施すれば、後願特許発明A+B+Cを不可避的に実施することになり、後願特許権者も、後願特許発明A+B+Cを実施すれば先願特許発明A+B+C0を実施することになり、両特許発明はいわゆる抵触関係にあるということができよう。なぜならば、先願特許権者は、自己の先願特許発明A+B+C0を実施すれば、不可避的にトリハロメタン除去用の効果を奏することになり、後願特許権者は、自己の後願特許発明A+B+Cを実施すれば、不可避的に塩素除去用の効果をも奏することになるからである。形式的には一見利用関係にないと思われる場合についても、特許発明同士について抵触関係が生じる場合があるということが言えよう。
3.7ファンクショナルクレームの場合
ファンクショナルクレームは一見広いクレームであるかのように見えるが、開示が不十分であるとして第三者との関係で実施例に限定されるという場合があり得る。米国では、ファンクショナルクレームの場合、実施例あるいは実施例との均等範囲に限定される。(条文)このような場合、実施例を除いた範囲は、穴空き範囲であるとも考えることができよう。穴空き特許の取扱いについては、別途論ずることとする。
3.8マーカッシュ形式の場合
マーカッシュ形式のクレームは一見広いクレームであるかのように見えるが、開示が不十分であるとして穴空き特許となる場合がある。例えば、形式的には開示されているように見えるが、先願特許明細書には製法と用途が記載されていない場合、このような特許発明には穴が空いていると考えられからである。(審査便覧18)を参照)
4.利用抵触関係の場合の取扱い
4.1外的付加の利用関係について
先願特許発明に外的付加を加えて後願特許発明とした場合、利用関係に有ることについてはそれ程議論の余地はなく、後願特許権者は、後願特許発明A+B+Cを実施すれば先願特許発明A+Bを実施することになるが、先願特許権者は先願特許発明A+Bを実施しても、後願特許発明A+B+Cを実施することにはならない。外的付加の利用関係については、専用権説、排他権説あるいは両権説のいずれを採っても結論は同じであろう。専用権説では特許法第72条は必要的規定であるのに対して、排他権説では第72条は確認的規定であると解釈される。両権説では、先願特許発明A+Bには、後願特許発明A+B+Cの排他権は及ばないので調整規定を設ける必要がないが、後願の専用権A+B+Cと先願の排他権A+Bとの盾矛の強弱について規定する必要があり、専用権説と同様、特許法第72条は必要的規定となる。
4.2内的付加等による抵触関係について
前述したように、内的付加の改良発明の場合内的付加の特質から抵触関係を生ずる場合が生じる。
先願特許権者は、先願特許発明A+Bを実施すれば、実施上不可避的に後願特許発明A+B+Cを実施することになり、後願特許権者も、後願特許発明A+B+Cを実施すれば、先願特許発明A+Bを実施することになるという場合が内的付加による抵触関係である。
特許法は、過誤特許の場合と同様、特許権同士の抵触関係を予定しておらず、どのように取扱われるかについて明確な規定はない。
このような場合、各説によって取扱いが分かれる。
排他権説に従えば、特許権の本質は排他権であるから、先願特許権者も後願特許権者双方とも後願特許発明A+B+Cを実施できず、実施すれば侵害を構成することになろう。
一方専用権説では、特許権同士の調整規定がないのであるから共に実施できるとするのか/あるいは特許法第72条の規定を類推適用して、先願優位の原則に従って専用権を調整して、先願特許権者のみが実施できるというのか?意見が分かれようが、後者の場合の方が良いのではなかろうか?
両権説では、やはり先願特許権者の実施については、先願特許権の専用権と後願特許権の排他権と盾矛の強弱を論ずる必要があり、結局は専用権説と同じ理由で、結論としては、私見では有るが過誤特許の場合と同様に取扱うのがベストであろう。同一発明に対しては、先願特許権者のみに専用権を与えると言うのが特許制度の本質であるからである。抵触特許発明については、先願優位の原則に従って先願特許権者のみに専用権を附与することにすれば、先願特許権者が先願特許発明の実施できるか否かについて、一々裁判所で争う必要も無く、後願特許権者は実施を確保するためには実施許諾を申し入れれば良いからである。
4.3穴空き特許の場合
穴空き特許の場合は、利用関係すら否定され、先願特許権者は先願特許発明A+Bを実施することができ、かつ後願特許権者も後願特許発明A+B+Cを自由に実施することができる。形式には利用関係にあるが、実質的には、先願特許発明A+Bの範囲には、後願特許発明A+B+Cは何ら開示がなく、穴が空いていると考えられるからである。この場合、専用権説、排他権説、両権説のいずれを採っても同じ結論となる。
先発メーカーは、穴空き特許となるのを防止すべくスキのない特許を取得しようと努力する。一方、後発メーカーは、先発メーカーの穴空き特許の穴空き部分に後願特許を取得することによって、相手のパンチを掻い潜って、自らのパンチのみを叩き込むいわゆる後の先を取ろうとするのである。19)
4.4その他
同日の利用関係にある場合、両権説ではどのように取扱ったら良いのであろうか?出願日に関しては両権利は全く対等であり、専用権と排他権のどちらを優先させるかで決る問題であるが、本来的には、特許要件の先願主義のような木目細かい調整規定が必要なのかも知れないが、現行法ではそれがない以上、法目的に照らして、発明の利用の観点から、両権利者とも実施できるとした方が産業政策に合致しているのではなかろうか?同日の過誤特許についても同様に、両権利者とも実施できるとした方が産業政策的に合致していると考えられるのではなかろうか?
以上のように、両権説は、現行法についても矛盾無く説明できるので、例えば盾と矛の関係をイメージして権利調整を図っているので現実にも対応していると考えられよう。
5.諸外国との比較
5.1米国との比較
米国の特許権は排他権で規定されており、先願特許権者は、後願特許発明A+B+Cを実施することができないのであり、従って、先願特許権者、後願特許権者双方とも後願特許発明A+B+Cを実施することができないこととなる。実施しようとしても、米国には裁定制度の規定はなく、後願特許発明A+B+Cの実施は当事者同士の話し合いに委ねられている。結局、後願特許発明A+B+Cを実施しようとしなければ、双方ともクロスライセンスすることになり、後は条件を追求することになるであろう。裁定制度の規定が有れば、後願特許発明の実施の奨励には繋がろうが……。
5.2欧州との比較
欧州と言っても、EPは、特許取得までであり、特許取得後はそれぞれの国の法律に従わざるを得ず属地主義に従うこととなる。
しかし、EP加盟の欧州各国は排他権として規定されており、米国の場合と同様に、先願特許権者、後願特許権者ともに後願特許発明A+B+Cを実施することができない。
欧州では、日本と同様、裁定制度を規定している国も有るが、米国と同様に、裁定制度を取らず、当事者の話し合いに委ねている国もある。(英国、伊国、オランダ等)
5.3条約との関係
TRIPs協定では、特許の排他的権利を規定している。(TRIPs協定第28条)我国特許法はTRIPs協定に違反するのであろうか?
しかし、各国は、通常の実施を不当に妨げず、かつ特許権者の正当な権利を不当に害さない場合には、TRIPs協定の特許権の効力を定めることができる旨の規定されているので、我国特許法第68条違反とはならないであろう。
また、パリ条約も、各国が排他的効力についての例外規定を設けることを認めている。(パリ条約5条A(2))
6.結論
先願特許発明と後願特許発明の利用関係において、主として両権説の立場に立って、先願特許権者が、後願特許発明A+B+Cを自由に実施できるか否かについて論じてきた。両権説は非常に分かりが良く、盾矛の強弱で論ずればよく妥当と考えられる。両権説では、先願特許発明A+B、後願特許発明A+B+Cは、以下のように取扱われるであろう。
(1)外的付加の場合の利用関係が生じる場合は、先願特許権者は先願特許発明A+Bを実施できるが、後願特許権者は後願特許発明A+B+Cを実施することができない。
(2)内的付加等の抵触関係の場合は、先願特許権者は先願特許発明A+Bを実施できるが、後願特許権者は後願特許発明A+B+Cを実施することができないと解すべきであろう。
(3)いわゆる穴空き特許の場合は、先願特許権者は先願特許発明A+Bを、後願特許権者は後願特許発明A+B+Cをともに実施することができる。
7.おわりに
技術の累積的進歩を図っていくという特許法の目的から、権利の調整は重要である。種々なケースの場合について考察することによって、本論説によって、特許権同士にも抵触関係(過誤特許の抵触関係以外の抵触関係)が生ずる場合があることを指摘できたことは、非常に有意義であろう。我国の特許法における抵触関係の取扱いは、両権説に従えば、先願優位の原則により先願者のみが実施でき後願者は実施できないと解するのが妥当であろう。
筆者は、本論説において、特許権は専用権と排他権との両方を有することを本質とする両権説を提案した。両権説は専用権説と排他権説の特許権の本質を一つとする説とは相異する。両権説は、均等論が適用された場合、排他権が拡大するのか専用権が拡大するのか問題となるが、両権説はこのような事態にも盾矛の強弱論を展開することにより木目細かく対処できるので優れた説であろう。
最後に、本論説を纏める当って色々とご教授いただきました関係各位に深く感謝の念を表します。
注記
1) 利用関係とは、後願権利内容を実施すれば、先願権利内容を実施することになるが、その逆は成立しない関係をいう。
2) 抵触関係とは、一方の権利内容を実施すれば、他方の権利内容を実施することになり、他方の権利内容を実施すれば、一方の権利内容を実施することになる関係をいう。
3) 外的付加とは、被改良発明の構成要件の概念とは無関係な構成要件を付加して改良発明とすることをいうものと一般には考えられている。
4) 内的付加とは、被改良発明の構成要件の上位概念をより具体的な下位概念に限定することによって改良発明とすることをいうものと一般には考えられている。
5) 専用権説とは、特許権の本質は、自己の特許発明を独占的に実施できる権利であるとして、特許法の条文解釈を行なう立場の説である。
6) 吉藤幸朔著、熊谷健一補訂「特許法概説(第12版)」有斐閣発行, p.457
7) 専用権説では、特許法第68条の「占有する」ことを担保すべく排他権を有すると説明するのが特徴である。専用権説では、主は専用権で、排他権は専用権を担保するためであり従とする。
8) 排他権説は、特許権の本質は、排他権であるとして、特許法の条文解釈を行なう立場の説である。
9) 関西大学法学研究所 研究叢書 第18冊(1977)別冊
10) 超紐理論では、中間子は、クォークと反クォークはグルーオンというゲージ粒子のひもで結び付けられて構成されているとするが、このような構成を採るのが本質であり、クォークと反クォークを単独に取り出すことはできない。
このことは、磁石を二つに切って、N極だけを取り出そうと試みてみても二つに切るや否や新しいN極、S極の一対が生じてしまうという磁石の性質とよく似ている。
11) 吉藤幸朔著、熊谷健一補訂「特許法概説(第12版)」有斐閣発行, p.460
12) 吉藤幸朔著、熊谷健一補訂「特許法概説(第12版)」有斐閣発行, p.458〜p.459
13) 吉藤幸朔著、熊谷健一補訂「特許法概説(第12版)」有斐閣発行, p.460
14) 特許庁編 〈財〉発明協会発行 特許実用新案 審査基準 第Ⅱ部 特許要件 第3章 特許法第29条の2p.4〜 5、第4章 特許法第39条p.7〜8を参照。
15) 数値限定発明は選択発明の一種であり、特許要件と特許後の特許権の効力範囲の関係が問題点として論じられている。
16) 特許庁編 〈財〉発明協会発行 特許実用新案 審査基準 第Ⅱ部 特許要件 第2章 新規性・進歩性 p.4〜5を参照。
17) 用途限定物の発明を取上げたのは、説明が少しでも分かり易くなれば良いと思ったからである。なお、我国では実務上用途限定物の発明の特許が認められている。
18) 審査便覧→製法と用途
19) 佐藤富徳著「良い明細書の作成方法」パテント1998 Vol.51 No.8 p.66〜67
弁理士・行政書士 佐藤富徳